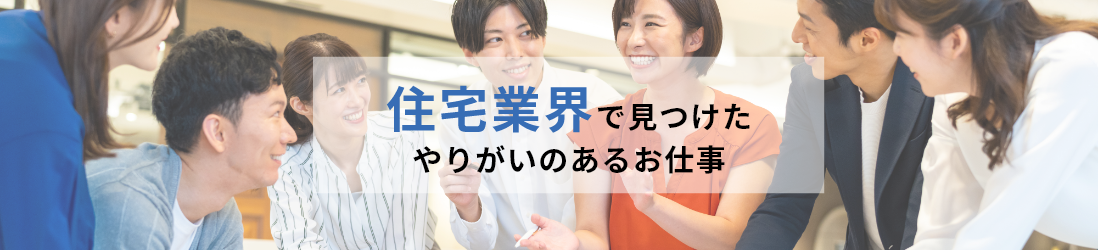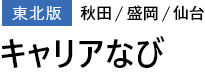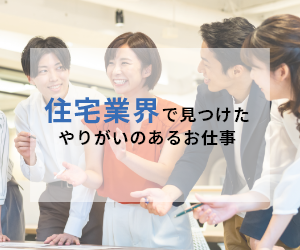東北の住宅業界の現場監督に転職するには資格は必要ない?
2024/01/26

現場監督の需要は今後増加する見通しです。しかし、建設業界では高齢化と人材不足が問題で、特に若い労働力の確保が課題です。現場監督になるためには主任技術者と監理技術者の2つの資格が必要です。仕事は過酷ですが経験を積むことで高収入が可能であり、キャリアアップの機会も豊富です。
増え続ける現場監督の需要と必要な資格
時代の変化や技術の進歩により、仕事の需要が減少することがあります。AIの普及により、将来的には不要とされる職種も出てきています。そのため、転職を考える際には、選んだ職業が今後も求められるか、収入を安定させられるかを考えることが重要です。こちらでは、東北地域の住宅業界で現場監督として転職を検討している方々に向けて、現場監督の需要や必要な資格やスキルについて紹介します。
◇現場監督の需要はあるのか?
建物の老朽化と建設業界の成長に伴い、現場監督の需要が高まっています。一方で、建設業界では従業員の高齢化や人材不足が課題となっており、現場監督の役割が重要視されています。
・建物の老朽化
高度経済成長時代に建設された建物や施設が古くなり、修繕や建て替えが必要です。国土交通省のデータによれば、地域の施設管理と更新費用は2013年には約3.6兆円でしたが、2023年には約4.3~5.1兆円に増加し、2033年には約4.6~5.5兆円に増える見込みです。
・建設業界の人材需要の増加
高度経済成長期に建てられた建物やインフラ施設は、老朽化が進んでおり、修繕や建て替えが必要になっています。国土交通省が示す「建設産業の現状と課題」によれば、地域のインフラ施設の管理や更新にかかる費用は、2013年の約3.6兆円から、2023年には約4.3~5.1兆円に増加し、2033年にはさらに増えて約4.6~5.5兆円に達すると予測されています。
一方で、建設業界では建設投資が増加しており、これに伴う需要が高まっています。しかし、建設業界の労働者数は減少傾向にあります。この現象の主な要因は、労働者の高齢化です。2015年の調査によれば、建設業で働く人のうち、55歳以上が約34%を占め、29歳以下はわずか11%です。団塊の世代が2025年に後期高齢者となり、退職することで、人材不足は一段と深刻化するでしょう。
また、少子高齢化と出生率の低下も、建設業界における人材確保の難しさに寄与しています。全産業の就業者数が増加している中で、建設業界の労働者数は1997年から2015年にかけて約685万人から500万人に減少しました。このため、建設業界における人材の需要は増加し、現場監督の職種への需要も高まっています。
◇必要な資格とスキル
現場監督になるために、特別な資格が必要なわけではありません。ただし、工事の種類や一定の規模を超える場合、特定の資格を持つ人を配置する必要があります。これらの資格は、主任技術者資格と監理技術者資格の2つで、どちらも国が認定したものです。
現場監督に必要なスキルとしては、コミュニケーション能力、リーダーシップ力、リスク管理能力、多くの仕事を同時にこなす能力などが挙げられます。
現場監督のキャリアをつかむための道

主任技術者と監理技術者の資格を取得するには、それぞれの資格に必要な条件を満たす必要があります。
◇主任技術者
主任技術者の資格を取得するためには、以下の方法があります。
1. 指定学科を卒業し、一定の実務経験を積む
– 高等学校の指定学科を卒業後は5年以上の実務経験が必要です。
– 高等専門学校の指定学科を卒業後は3年以上の実務経験が必要です。
– 大学の指定学科を卒業後は3年以上の実務経験が必要です。
– その他の学歴の場合は10年以上の実務経験が必要です。
2. 特定の資格を取得する
一級・二級建設機械施工技士試験、土木の施工管理技士、二級建築士などの資格を取得することでも、受験資格を得ることができます。
3. 複数業種の実務経験を積む
指定された2つの業種で合計12年以上の実務経験が必要で、そのうちの1つが8年以上の実務経験が必要です。
◇監理技術者
監理技術者の資格を取得するためには、以下の条件が必要です。
1. 原則的に建設会社との雇用契約が必要
2. 特定の資格を取得し、実務経験を積む
必要な資格は、申請する工事の種類によって異なるため、具体的な資格は工事に関連して確認する必要があります。
◇まずは資格をとろう
住宅業界での転職を考えているなら資格を取得することを推奨します。
資格を取得するために仕事をしながら経験を積むことも可能ですが、新しい業界での仕事を始めながら資格取得を目指すよりも、今から勉強して資格を取得する方が容易です。転職前に資格を持っていると、より良い転職条件を得ることができるメリットがあります。
また、実務経験を積んで主任技術者の資格を目指す場合、3年以上かかることがありますが、国家資格を取得すれば実務経験を積む必要がなく、迅速に資格を取得できます。たとえば、二級建築士資格は難易度が低く、将来的に一級建築士を目指す際にも役立つため、住宅業界でのキャリアアップにも寄与します。
現場監督として働く問題点と年収
現場監督の平均年収は約458万円で、地域によって異なります。仕事は過酷で、仕事量が多く長時間労働が必要で、休みが取りづらいとされています。一方で、経験を積むことで高収入も可能であり、キャリアアップも見込めます。
◇現場監督の平均年収
求人ボックス給料ナビの情報によれば、現場監督の平均年収は約458万円で、初任給は約21万円、月給は約38万円です。ただし、この収入はスキルや経験、勤務先によって大きく異なり、経験を積むことで年収1,000万円以上も可能です。また、現場監督の年収は地域によっても異なり、最も高い平均年収は約504万円の神奈川県で、最も低いのは約348万円の佐賀県です。なお、派遣社員の平均時給は1,733円、アルバイト・パートは1,185円です。
◇きついと言われる現場監督の現状
現場監督の仕事は、一般的に過酷なものとされています。仕事量が多いため、現場監督は工事計画から事務作業まで幅広い業務を担当します。これには打ち合わせ、現場の巡回、事務処理などが含まれます。
元々仕事が多い職種であるため、長時間労働が必要です。さらに、人手不足の問題があるため、労働時間がさらに長くなることがあります。
休みが取りづらいのも、現場監督の特徴です。建物の建設には常に納期が設定されていますが、事故や天候の影響で工事がスケジュール通りに進まないことがよくあります。そのため、繁忙期には休日出勤が必要とされることもあります。
さらに、現場監督は事務作業だけでなく、工事現場で進捗状況を確認したり、安全管理を行ったりする必要があります。そのため、事故に巻き込まれてケガをするリスクも存在します。
現場監督の需要が高まっている背景には、建物の老朽化と建設業界の成長があります。老朽化した建物や施設の修繕や建て替えが必要であり、そのために現場監督の役割が重要視されています。
国土交通省によるデータでは、施設管理と更新にかかる費用が増加傾向にあり、今後も需要は高まるでしょう。しかし、建設業界では労働者の高齢化や人材不足も問題となっており、特に若い労働力の確保が課題です。
現場監督になるために必要な資格は、主任技術者と監理技術者の2つです。主任技術者には、指定学科の卒業と実務経験、特定の資格取得、複数業種の実務経験などが求められます。
監理技術者は建設会社との雇用契約が基本で、工事に関連した資格取得と実務経験が必要です。資格取得は、住宅業界での転職を考える際に役立つステップであり、実務経験を積むことなく資格を取得できる国家資格も存在します。
現場監督の平均年収は約458万円で、地域によって異なります。仕事は過酷で、長時間労働と休みが取りづらい特徴があり、事故に巻き込まれるリスクも存在します。しかし、経験を積むことで高収入も可能であり、キャリアアップの機会も広がります。
現場監督としてのキャリアを築くためには、資格取得が一つの近道とされており、これによって転職時の条件面でも有利になるでしょう。